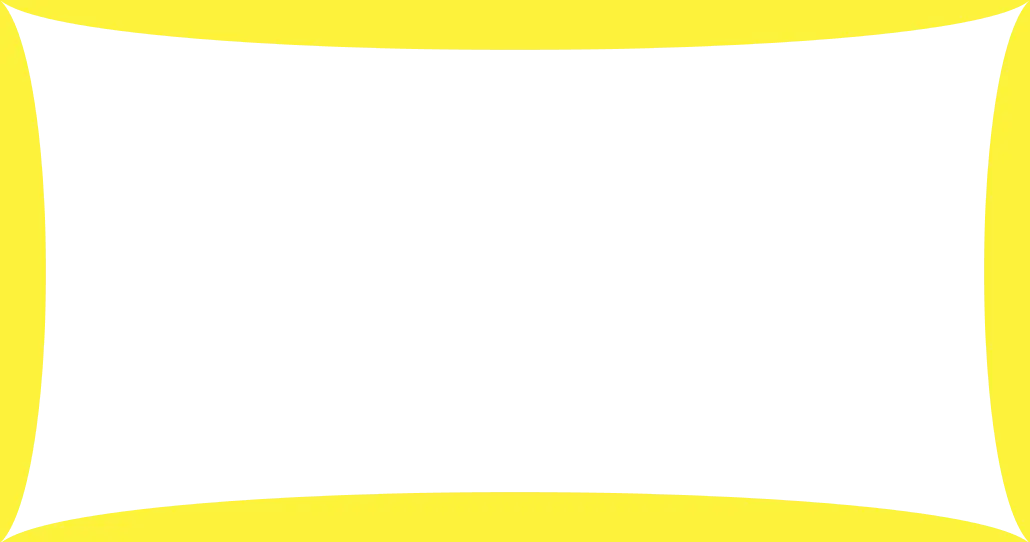Tanzan Jinja things to do, attractions, restaurants, events info and trip planning

Basic Info
Tanzan Jinja
319 Tonomine, Sakurai, Nara 633-0032, Japan
4.3(1.5K)
Closed

tickets
Save
spot
spot
Ratings & Description
Info
Tanzan Shrine, also known as the Danzan Shrine, the Tōnomine Shrine and the Tōnomine Temple, is a Shinto shrine in Sakurai, Nara Prefecture, Japan. It is located 5km from Ishibutai Kofun.
Cultural
Outdoor
Family friendly
attractions: Tanzan Jinja Jusanjunoto (Thirteen Story Pagoda), restaurants: , local businesses: Mausoleum Hall, Koyu Teahouse, Goharetsuzan, Goharetsuzan
 Learn more insights from Wanderboat AI.
Learn more insights from Wanderboat AI.Phone
+81 744-49-0001
Website
tanzan.or.jp
Open hoursSee all hours
Thu8:30 AM - 4:30 PMClosed
Plan your stay

Pet-friendly Hotels in Asuka
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Affordable Hotels in Asuka
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

The Coolest Hotels You Haven't Heard Of (Yet)
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Trending Stays Worth the Hype in Asuka
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.
Reviews
Live events

Osaka mountain hike and trout fishing
Mon, Feb 16 • 8:45 AM
586-0015, Osaka, Kawachinagano, Japan
View details

Cook Traditional Bento in a Local Home in Nara
Fri, Feb 13 • 11:00 AM
636-0151, Nara, Ikaruga, Ikoma District, Japan
View details

Cycle and explore rural Osaka
Fri, Feb 13 • 9:00 AM
582-0007, Osaka, Kashiwara, Japan
View details
Nearby attractions of Tanzan Jinja
Tanzan Jinja Jusanjunoto (Thirteen Story Pagoda)

Tanzan Jinja Jusanjunoto (Thirteen Story Pagoda)
4.5
(78)
Closed
Click for details
Nearby local services of Tanzan Jinja
Mausoleum Hall
Koyu Teahouse
Goharetsuzan
Goharetsuzan

Mausoleum Hall
4.3
(17)
Click for details

Koyu Teahouse
4.6
(9)
Click for details
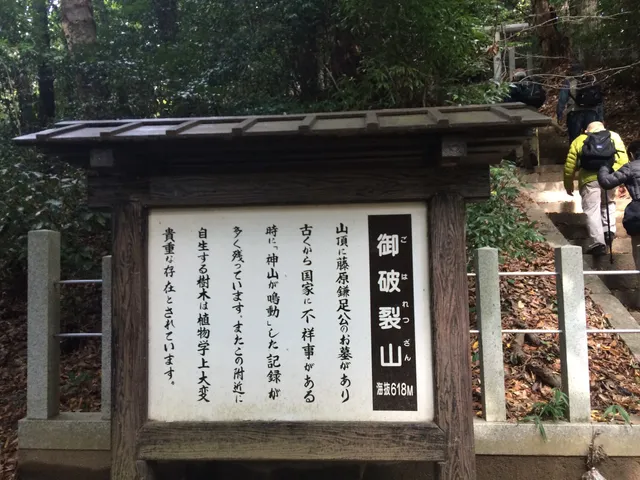
Goharetsuzan
3.9
(8)
Click for details

Goharetsuzan
3.9
(9)
Click for details