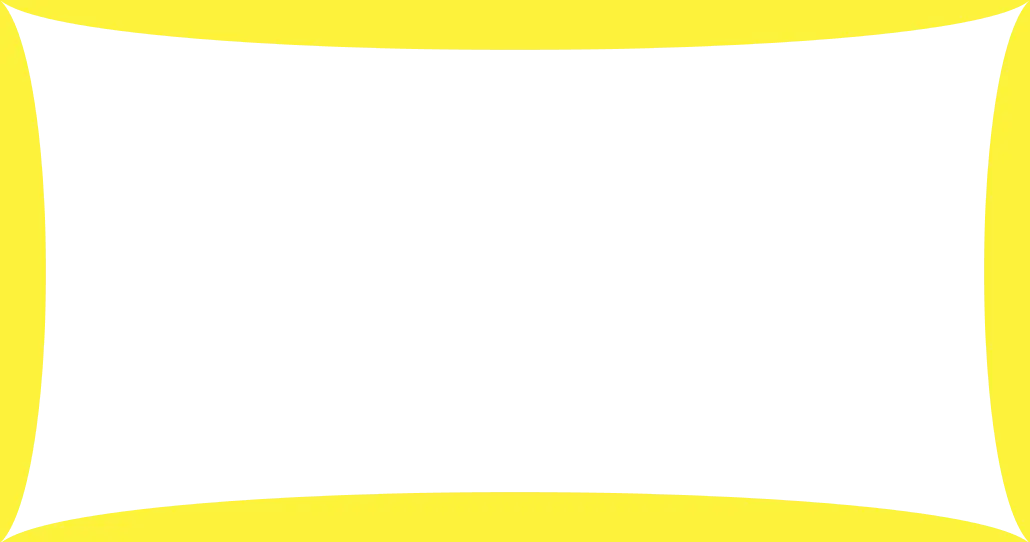Kagami Shrine things to do, attractions, restaurants, events info and trip planning

Basic Info
Kagami Shrine
1289 Kagami, Ryuo, Gamo District, Shiga 520-2573, Japan
3.9(60)
Open until 12:00 AM
Save
spot
spot
Ratings & Description
Info
Kagami-jinja is a Shinto shrine located in Karatsu, Saga prefecture, Japan. The shrine is at the base of Mount Kagami in Genkai Quasi-National Park. It is now called Matsura Sōchinshu Kagami-jinja, and formerly known as the name of Kagami no mikoto Byōgū, Kagami-gū, Matsuura-gū, Itabitsu-sha and Kuri Daimyōjin.
Cultural
Scenic
attractions: , restaurants: My curry cafeteria wheel, local businesses:
 Learn more insights from Wanderboat AI.
Learn more insights from Wanderboat AI.Phone
+81 748-58-0959
Website
shiga-jinjacho.jp
Open hoursSee all hours
ThuOpen 24 hoursOpen
Plan your stay

Pet-friendly Hotels in Ryuo
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Affordable Hotels in Ryuo
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

The Coolest Hotels You Haven't Heard Of (Yet)
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Trending Stays Worth the Hype in Ryuo
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.
Reviews
Live events

京都府立植物園:LIGHT CYCLES KYOTO (ライトサイクル京都)
Thu, Feb 12 • 6:00 PM
京都市左京区下鴨半木町, 606-0823
View details

プライベート京都ウォーキングツアー 寺院、伝統、隠れた逸品
Thu, Feb 12 • 7:00 AM
京都市東山区清水八坂上町388, 605-0862
View details

京都:築150年の町家で書道教室
Thu, Feb 12 • 9:15 AM
京都市東山区桝屋町349−19, 605-0826
View details
Nearby restaurants of Kagami Shrine
My curry cafeteria wheel

My curry cafeteria wheel
3.9
(230)
Closed
Click for details