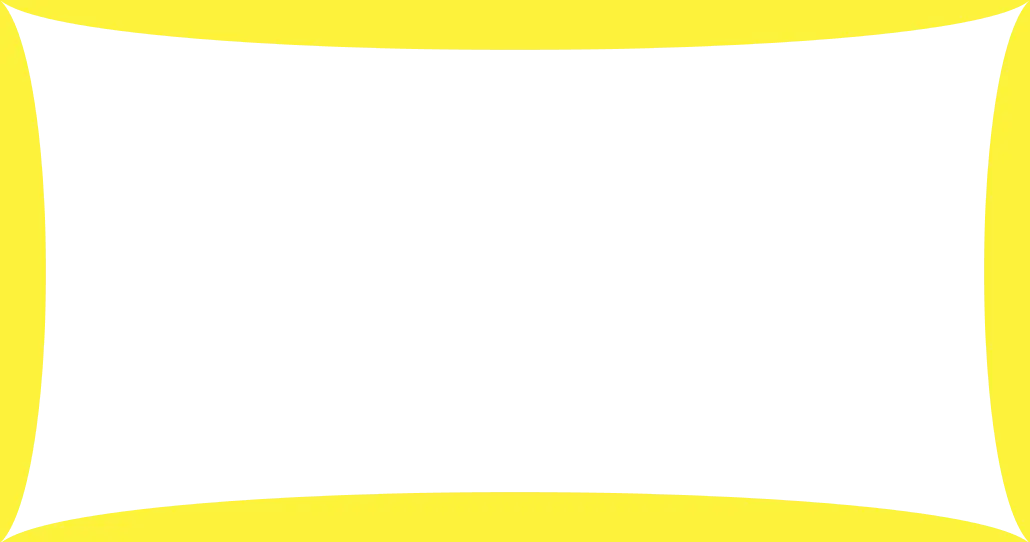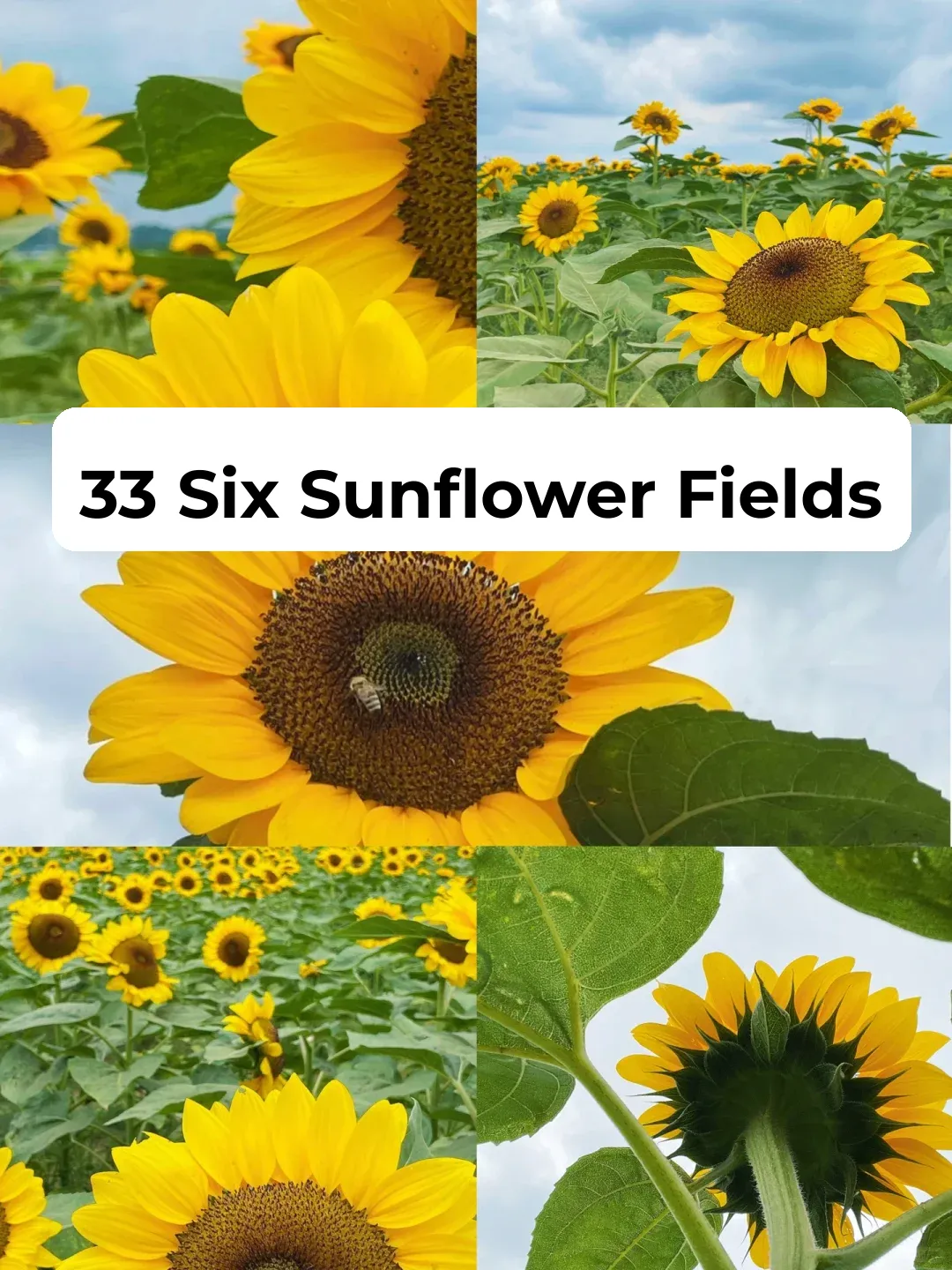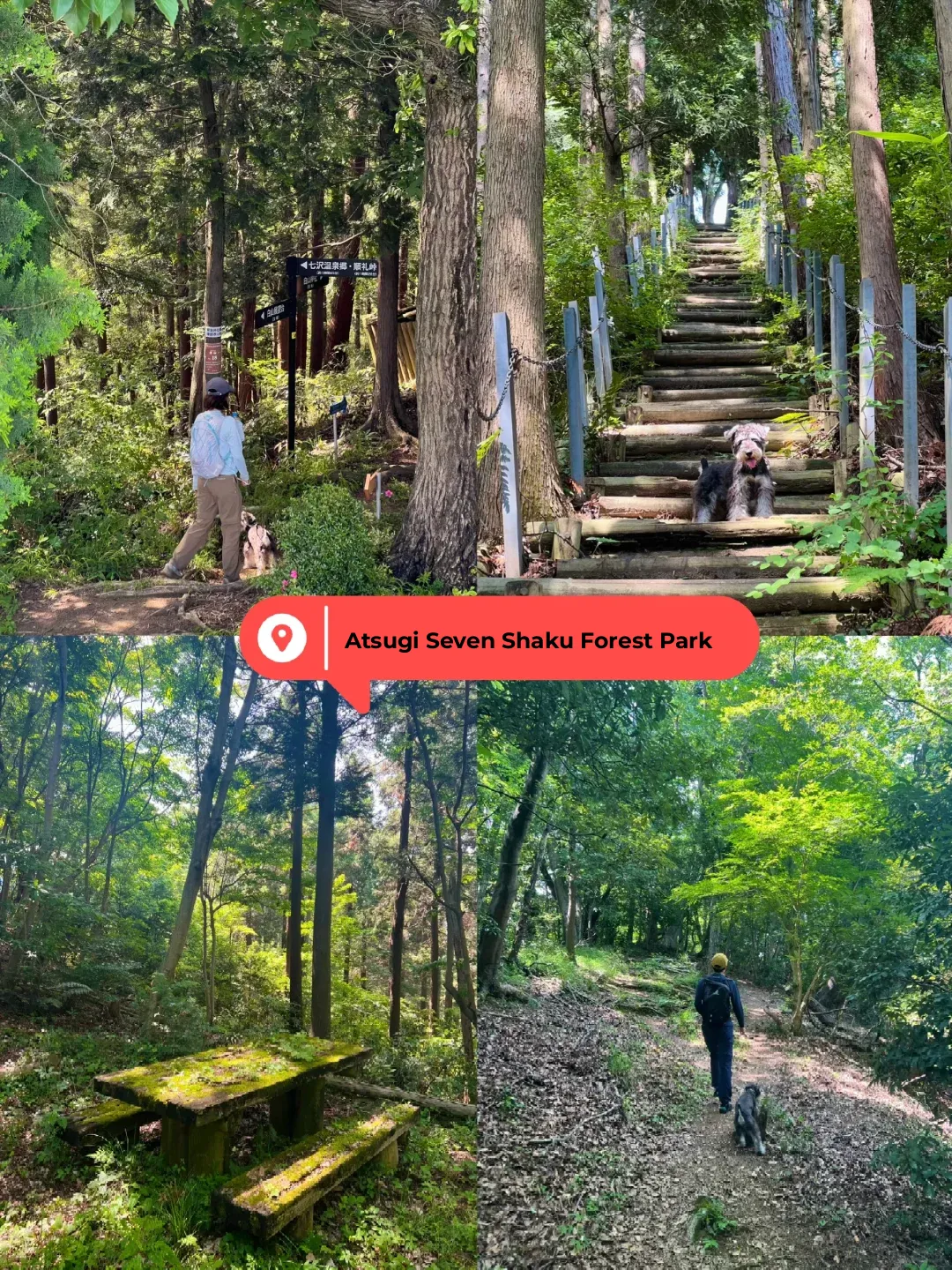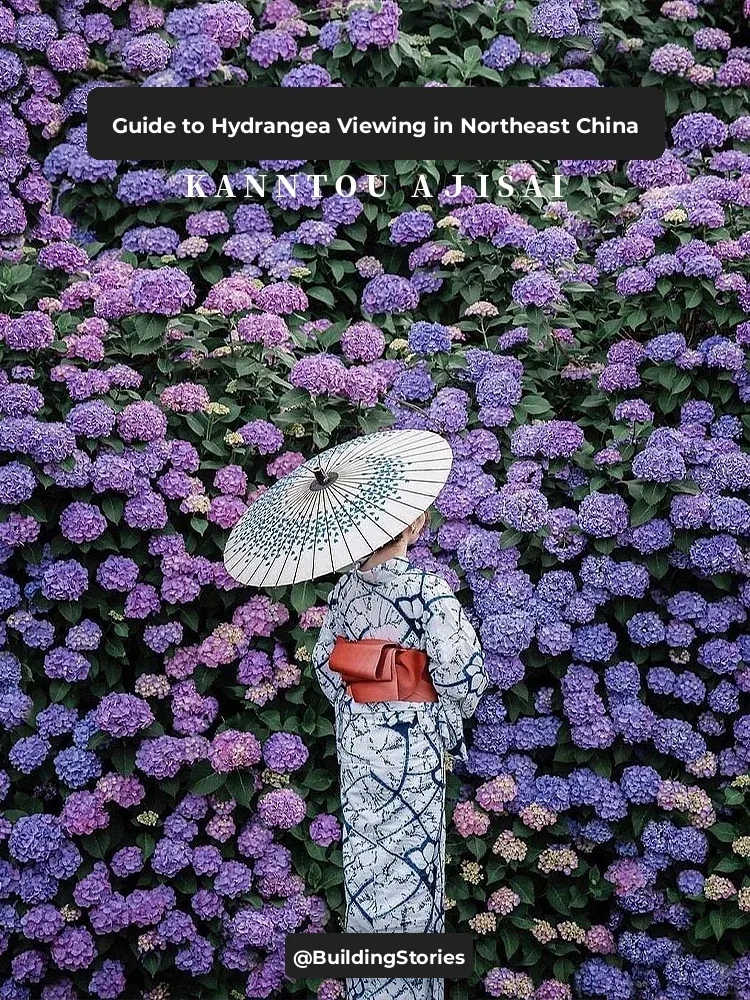Hakusan Shrine things to do, attractions, restaurants, events info and trip planning
Basic Info
Hakusan Shrine
5 Chome-31-26 Hakusan, Bunkyo City, Tokyo 112-0001, Japan
4.0(1.2K)
Open until 12:00 AM
Save
spot
spot
Ratings & Description
Info
Cultural
Family friendly
attractions: Toyo University Hakusan Campus, Hakusan Park, Inoue Enryô Memorial Museum, Koishikawa Botanical Garden, Nankoku-ji, Green house, Azalea garden, Kichijōji, Fukunoyu, Harimazaka Sakura-namiki, restaurants: Komugiko, Ore No Ikiru Michi, Eigakan Jazz, Eigakan Jazz, FRESHNESS BURGER Hakusaneki-mae, Yasai cafe KuKuri, Chōtoku, Yayoiken Hakusan, Trattoria Dadini, Bar INOUE, local businesses: MASTER KEBAB(HALAL FOOD), Shinkoji, Ryu-un Zen-in, Matsumoto Kiyoshi, Renkyūji, Sanja Shrine, Azalea Garden, Hon-Komagome Station, Gonjōin Temple, Jippōji
 Learn more insights from Wanderboat AI.
Learn more insights from Wanderboat AI.Phone
+81 3-3811-6568
Website
tokyo-jinjacho.or.jp
Open hoursSee all hours
ThuOpen 24 hoursOpen
Plan your stay

Pet-friendly Hotels in Tokyo
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Affordable Hotels in Tokyo
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

The Coolest Hotels You Haven't Heard Of (Yet)
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Trending Stays Worth the Hype in Tokyo
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.
Reviews
Live events

Drive Tokyo’s car culture in a Nissan Skyline
Fri, Feb 27 • 5:30 PM
150-0047, Tokyo Prefecture, Shibuya, Japan
View details

Explore Tokyo’s music scene with an insider
Sun, Mar 1 • 5:00 PM
150-0043, Tokyo Prefecture, Shibuya, Japan
View details

TYFFONIUM 新宿:IT/イット カーニバル
Thu, Feb 26 • 11:20 AM
東京都新宿区西新宿2-2-1 京王プラザホテル 南館2F (2-chōme-2-1 Nishishinjuku, Shinjuku City), 160-8330
View details
Nearby attractions of Hakusan Shrine
Toyo University Hakusan Campus
Hakusan Park
Inoue Enryô Memorial Museum
Koishikawa Botanical Garden
Nankoku-ji
Green house
Azalea garden
Kichijōji
Fukunoyu
Harimazaka Sakura-namiki

Toyo University Hakusan Campus
4.3
(226)
Open 24 hours
Click for details

Hakusan Park
4.2
(81)
Open until 12:00 AM
Click for details

Inoue Enryô Memorial Museum
3.8
(158)
Open until 4:45 PM
Click for details

Koishikawa Botanical Garden
4.3
(1.4K)
Open until 4:30 PM
Click for details
Nearby restaurants of Hakusan Shrine
Komugiko
Ore No Ikiru Michi
Eigakan Jazz
Eigakan Jazz
FRESHNESS BURGER Hakusaneki-mae
Yasai cafe KuKuri
Chōtoku
Yayoiken Hakusan
Trattoria Dadini
Bar INOUE

Komugiko
4.3
(266)
Closed
Click for details

Ore No Ikiru Michi
3.8
(536)
Open until 3:00 PM
Click for details

Eigakan Jazz
4.6
(71)
Closed
Click for details

Eigakan Jazz
4.6
(67)
Closed
Click for details
Nearby local services of Hakusan Shrine
MASTER KEBAB(HALAL FOOD)
Shinkoji
Ryu-un Zen-in
Matsumoto Kiyoshi
Renkyūji
Sanja Shrine
Azalea Garden
Hon-Komagome Station
Gonjōin Temple
Jippōji

MASTER KEBAB(HALAL FOOD)
4.7
(172)
Click for details

Shinkoji
4.0
(21)
Click for details

Ryu-un Zen-in
4.1
(8)
Click for details

Matsumoto Kiyoshi
3.2
(20)
Click for details